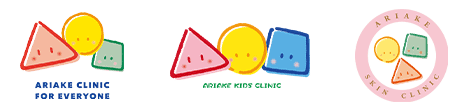RSウイルス感染症について 注意したいポイントと対策
こんにちは、有明こどもクリニック豊洲院院長の「のりちゃん先生」こと、村上典子です。
RSウイルス感染症は、特に乳幼児にとって注意が必要な感染症の一つです。毎年秋から冬にかけて流行し、年齢や体調によって症状の重さが異なります。今回は、RSウイルス感染症の特徴や症状、注意点、予防法について詳しくお話しします。

RSウイルス感染症とは?
RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)は、乳幼児のほとんどが2歳までに感染すると言われる非常に一般的なウイルスです。初感染は重症化する可能性が高いため、特に小さな赤ちゃんを育てているご家庭では注意が必要です。
✅ 感染経路
・飛沫感染:くしゃみや咳などで飛び散ったウイルスを吸い込むことで感染します。
・接触感染:ウイルスがついた手で顔や口を触ることで感染します。
✅ 流行の時期
主に秋から冬にかけて流行しますが、近年は季節を問わず見られることもあります。
RSウイルス感染症の症状
RSウイルス感染症の症状は、年齢や感染の程度によって異なります。特に6か月未満の乳児や、早産児、持病のあるお子さんでは重症化しやすい傾向があります。
✅ 典型的な症状
・鼻水や咳、くしゃみなど風邪のような症状から始まります。
・発熱(軽度〜高熱の場合も)
・食欲低下、元気のなさ
✅ 重症化した場合の症状
・呼吸困難:ゼーゼー(喘鳴)が聞こえる、呼吸が速い、息が苦しそう
・哺乳不良:ミルクを飲めない
・ぐったりしている、顔色が悪い
・重症化すると、細気管支炎や肺炎を引き起こすことがあります。
特に注意が必要な子どもたち
次のような場合は、RSウイルス感染症にかかった際に重症化しやすいため、早めの対応が大切です。
・6か月未満の乳児
・早産児
・慢性肺疾患や先天性心疾患を持つお子さん
・免疫力が低下しているお子さん
治療法と対応
RSウイルス感染症には、残念ながら特効薬はありません。治療は基本的に対症療法となります。
✅ 対症療法のポイント
・発熱への対応:必要に応じて解熱剤を使用(アセトアミノフェンなど)。
・水分補給:脱水を防ぐため、こまめに水分を与えます。
・鼻づまりのケア:吸引器を使って鼻水を取り除くことで呼吸を楽にします。
・安静:体力を回復させるため、しっかり休ませましょう。
✅ 入院が必要になる場合
・呼吸困難(息が苦しそう、ゼーゼーがひどい)
・哺乳量が極端に減る(半分以下しか飲めない)
・顔色が悪い、ぐったりしている
RSウイルス感染症の予防法
RSウイルスは感染力が強いため、家庭内での予防がとても重要です。また、近年、新しい予防方法も加わり、重症化リスクを減らす選択肢が広がっています。
✅ 基本的な予防法
・手洗い:外出から帰ったら必ず手洗いを徹底します。
・咳エチケット:家族も含め、咳やくしゃみをするときはマスクやティッシュで口を覆います。
・清潔な環境を保つ:おもちゃやドアノブなど、子どもが触れる場所を定期的に消毒しましょう。
・人混みを避ける:流行時期は特に人混みや密閉された場所を避けるようにします。
✅ 母体のワクチン接種:アブリスボ
アブリスボは、RSウイルス感染症の予防に有効なワクチンです。妊娠36週未満の妊婦さんが接種することで、赤ちゃんに抗体を移行し、生後の重症化リスクを下げることが期待されます。
接種の適応については産科の主治医に相談してください。当院でも積極的に接種しております。
✅ 重症化リスクの高いお子さんへの予防薬
パリビズマブ(商品名:シナジス)という予防薬が使用される場合があります。早産児や持病のあるお子さんなど、医師の判断で投与が検討されます。

RSウイルス感染症は、ほとんどの子どもが経験するウイルス感染症ですが、小さな赤ちゃんや基礎疾患を持つお子さんにとっては、注意が必要な病気です。予防策を講じることで重症化のリスクを減らせるため、特にワクチンや予防薬の選択肢については、医師に相談して適切な対応を検討しましょう。
次回も役立つ情報をお届けしますのでお楽しみに!