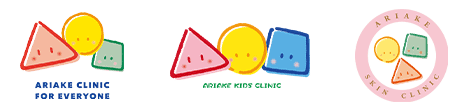赤ちゃんや子どもの「人見知り」について:成長の証と上手な付き合い方
こんにちは、有明こどもクリニック豊洲院院長の「のりちゃん先生」こと、村上典子です。
お子さんが「急に知らない人を見て泣いてしまう」「親から離れられなくなる」など、赤ちゃんや子どもの人見知りに困っているパパママも多いのではないでしょうか?
人見知りは、多くの親御さんが心配するポイントですが、実はこれはお子さんの成長過程において、とても大切なステップなんです!
今回は、人見知りが起こる理由や時期、親としてできるサポートの仕方についてお話しします。

人見知りって何?なぜ起こるの?
人見知りは、赤ちゃんが「親やいつも一緒にいる人」と「知らない人」を区別できるようになった証です。
これは、脳の発達や社会性の成長によって起こります。
💡 簡単に言えば…
「この人は知らないから不安だな。大好きなママやパパのそばにいたい!」という心のサインです。
✅ 人見知りはなぜ起こるの?(発達の視点)
・脳の発達:生後6か月頃になると、「親しい人」と「知らない人」の区別がつくようになります。
・愛着形成:親(養育者)への「信頼」がしっかり築かれているからこそ、知らない人に対して不安を感じます。
・社会性の始まり:「この人は誰?」と周囲への興味と警戒が芽生えた証拠です。
人見知りはいつから?どのくらい続くの?
✅ 人見知りが始まる時期
・生後6か月頃から1歳前後にかけて、多くの赤ちゃんが人見知りを始めます。
・ピークは1歳前後ですが、個人差が大きく、早い子もいれば遅い子もいます。
✅ 人見知りはいつまで続く?
・2歳になるといきなり大声で泣いたりすることは減ってきます。
・しかし、幼児期や小学校低学年になっても、初対面の大人や大勢の前で恥ずかしがるのはよくあることです。
年齢別の「人見知り」の特徴と対処法
🌱 生後6か月〜1歳頃:初めての人見知り期
✅ よくある様子:
・知らない人を見ると泣いてしまう
・親にしがみついて離れない
・抱っこを求めてくる
✅ 親ができるサポート:
・無理に抱っこさせない・近づけさせない:「怖い」と感じる相手に無理強いすると、不安が強まります。
・親が安心の存在であることを示す:「大丈夫だよ」「ママがそばにいるよ」と優しく声をかけます。
・慣れるまで時間をかける:同じ人と何度か会うことで安心感が生まれます。
🌿 1歳〜3歳頃:後追いと人見知りが重なる時期
✅ よくある様子:
・ママやパパが見えなくなると大泣きする(後追い)
・大勢の集まりで親から離れられない
・知らない人に話しかけられても答えられない
✅ 親ができるサポート:
・無理に「挨拶しなさい」と言わない:緊張している時は、親が代わりに挨拶をして見本を見せます。
・人前での恥ずかしさを尊重する:無理に注目を浴びせると逆効果です。
・「緊張するのは普通だよ」と伝える:「ママも初めての人は緊張するよ」と共感を示します。
🍃 3歳〜6歳頃:恥ずかしがり屋タイプの人見知り
✅ よくある様子:
・幼稚園や保育園で新しい先生や友達に緊張する
・知らない場所で親の後ろに隠れる
・発表会や集団活動で固まってしまう
✅ 親ができるサポート:
・安心できる「慣れ」から始める:例えば、「親と一緒に遊ぶ → 親は少し離れて見守る」というステップを踏む。
・自己紹介や挨拶を一緒に練習する:家で「こんにちは」「ありがとう」などロールプレイをしておくと安心します。
・成功体験を褒める:「先生に挨拶できたね!すごいね!」と、小さな一歩を認めます。
親御さんが気をつけたいこと
🚫 やってはいけないこと
・「恥ずかしがり屋で困る」と子どもの前で言う:
→ 「自分は人前でうまくできない」と自己肯定感が下がります。
・「なんでできないの?」と責める:
→ 緊張は自然な反応なので、責められると不安が強くなります。
いつもと違う?こんなときは相談を!
多くの人見知りは成長とともに和らぎますが、パパママから見て日常生活に支障が出ていると感じたときには、ためらわず小児科に相談にいらしてください。
✅ 極端に他人を避けて、パニックになることが続く
✅ 同年代の子と全く関われない、または強い不安を感じる
✅ 話しかけられても全く反応せず、コミュニケーションが極端に困難
こうした場合は、発達特性(発達障害、社交不安障害など)が背景にある可能性もあります。

「人見知り」は社会性の第一歩!「うちの子は人見知りだからダメだ」ではなく、「慎重派でしっかり考えているんだね」と受け止めることが大切です。
「安心できる場所」として、子どもが親に頼れることは大きな心の支えになります。「少しずつでいいよ」と、子どものペースを大切にしましょう。
次回も役立つ情報をお届けしますのでお楽しみに!