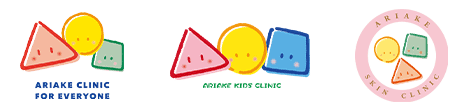起立性調節障害とは?朝起きられないのは怠けではありません!
こんにちは、有明こどもクリニック豊洲院院長の「のりちゃん先生」こと、村上典子です。
最近も、小学校高学年から中学生のお子さんで朝、起きられないのが原因で学校に行けないと訴えて受診される方がとても増えています。
「朝起きられない」「めまいがする」「学校に行きたくても体がつらい」など、お子さんの体調不良が続いていませんか?
もしかすると、それは「起立性調節障害(OD)」かもしれません。
起立性調節障害は、思春期の子どもに多くみられる自律神経の不調による病気で、「怠けている」「やる気がない」と誤解されることもあります。
今回は、起立性調節障害の原因・症状・治療法・親ができるサポートについて詳しくお話しします。

起立性調節障害(OD)とは?
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)は、自律神経の働きが乱れることで、血圧や心拍数の調節がうまくできなくなる病気です。
特に小学校高学年~中学生の思春期に多くみられ、成長期のホルモンバランスの変化やストレスが関係していると考えられています。
起立性調節障害の主な症状
起立性調節障害の子どもは、朝が特に辛く、「朝起きられない」「めまいがする」「立ちくらみがする」といった症状がよくみられます。
✅ 主な症状
・朝起きられない(昼頃まで体がだるい)
・立ちくらみやめまい(急に立つとふらつく)
・動悸・息切れ(少し動くだけで心臓がドキドキする)
・倦怠感(だるさ)(とにかく体が重く、やる気が出ない)
・頭痛や腹痛(特に午前中に強いことが多い)
・食欲不振(朝ごはんを食べたくない)
・午後から元気になる(午前中は動けなくても、午後には活動できることが多い)
💡 「午後になると元気になる」ことが特徴的で、周囲から「怠けているだけ」と誤解されやすい病気です。
起立性調節障害の原因
起立性調節障害は、自律神経の乱れによって血圧や心拍数の調整がうまくできなくなることが原因です。
自律神経には、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の2種類があり、これがバランスよく働くことで、私たちの体は血圧や心拍を調節しています。
しかし、二次性徴期の急激なホルモン変化やストレスの影響で自律神経のバランスが崩れると、血圧が急に下がったり、脳へ十分な血流が行かなくなったりして、めまいやだるさが出てしまうのです。
起立性調節障害の診断方法
起立性調節障害の診断には、「新起立試験」という検査が行われます。
✅ 新起立試験とは?
・横になった状態で血圧と脈拍を測る
・立ち上がり、時間ごとに血圧と脈拍の変化を測定する(10分間)
この検査で、血圧や心拍数が急に変化するかどうかを確認し、起立性調節障害の診断を行います。
起立性調節障害の治療と対策
起立性調節障害の治療は、生活習慣の改善が基本となります。
✅ 生活習慣の改善(基本の対策)
・水分をしっかりとる(1日1.5~2Lの水分補給)
・塩分を意識してとる(血圧を上げるために適量の塩分が必要)
・ゆっくり起きる(急に立ち上がらず、横になったままストレッチしてから起きる)
・適度な運動をする(寝たきりが続くと悪化するため、少しずつ動く習慣をつける)
・早寝早起きをする(スマホやゲームの時間をコントロールし、十分な睡眠をとる)
✅ 薬物療法(症状が強い場合)
生活習慣の改善だけでは症状が改善しない場合、薬による治療が行われることもあります。
💊 主な薬の種類
・昇圧剤(ミドドリン):血圧を安定させる
・自律神経調整薬(メトリジン、リズミック):自律神経の働きを整える
・漢方薬(補中益気湯など):体質改善を目指す
ただし、薬に頼るだけでなく、生活習慣の改善が何よりも大切です。
パパママができるサポート
起立性調節障害の子どもは、「朝起きられないことで周囲に責められ、精神的に追い込まれる」ことが少なくありません。
✅ 「怠け」ではなく「病気」であることを理解する
「甘えている」「気合で起きなさい」と言われると、子どもは自信を失い、さらに症状が悪化してしまうこともあります。
✅ 学校や先生と連携する
起立性調節障害について学校に伝え、登校時間の調整や午前中の負担を減らしてもらうなどの対応を相談することも大切です。
起立性調節障害とうまく付き合おう
✅ 起立性調節障害は、思春期に多い自律神経の病気であり、決して「怠け」ではありません。
✅ 生活習慣の改善が重要で、水分・塩分補給、適度な運動、睡眠の改善がカギになります。
✅ 無理に登校を強制せず、子どもの気持ちや体調に寄り添いながらサポートすることが大切です。

起立性調節障害は、更年期障害のちょうど裏返しです。誰にでも起こり得る体調変化ですが、二次性徴期が過ぎていけば落ち着いていきます。「いつか良くなる」という気持ちで、焦らず、少しずつ前向きに向き合っていきましょう!
次回も役立つ情報をお届けしますのでお楽しみに!